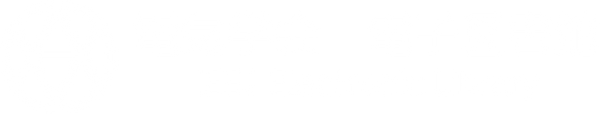「交流電化発祥の地」に係わる技術史について
「交流電化発祥の地」に係わる技術史について
カテゴリ: 研究会(論文単位)
論文No: HEE10004
グループ名: 【A】基礎・材料・共通部門 電気技術史研究会
発行日: 2010/01/14
タイトル(英語): History of engineering about the birthplace of railway AC electrification in Japan (The Senzan Line)
著者名: 白石 秀男(東日本旅客鉄道),林屋 均(東日本旅客鉄道)
著者名(英語): Shiroishi Hideo(East Japan Railway Company),Hayashiya Hitoshi(East Japan Railway Company)
キーワード: 交流電化|仙山線|交流-直流切替設備|交流機関車|技術史|発祥地|AC railway electrification|Senzan Line|AC-DC section|AC locomotive|History of engineering|Birthplace
要約(日本語): 昭和32年9月5日、わが国ではじめての交流電気機関車による営業運転が仙山線仙台・作並間で開始された。これは、昭和28年8月の国鉄交流電化調査委員会発足、それに続く2年間に及ぶ仙山線北仙台~作並間での交流電気鉄道の現地試験での努力が結実したものであり、その後の新幹線技術にも引き継がれる歴史的偉業であった。本稿では、交流電化に至った経緯、当時の技術的判断なども含めて整理し、紹介する。
要約(英語): The Senzan Line was AC electrified partly in 1953. The acquired technologies here were applied for the coming electric railway including Shinkansen and it was a remarkable achievement for the history of Japanese electric railway. The history and effort of AC railway electrification will be summarized in this paper.
原稿種別: 日本語
PDFファイルサイズ: 5,698 Kバイト
受取状況を読み込めませんでした