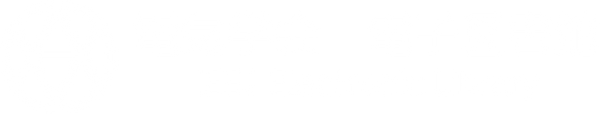江戸時代の人々にとってエレキテルとは何だったのか
江戸時代の人々にとってエレキテルとは何だったのか
カテゴリ: 研究会(論文単位)
論文No: HEE19024
グループ名: 【A】基礎・材料・共通部門 電気技術史研究会
発行日: 2019/10/04
タイトル(英語): hat is Erekiteru (Oerekitere) for People in Edo Period?
著者名: 西村 亮(鳥取大学)
著者名(英語): Ryo Nishimura(Tottori University)
キーワード: 摩擦起電機|エレキテル|平賀源内|江戸時代|電気技術史|静電気|Friction generator|Hiraga Gennai|Edo period|History of electric engineering|Electrostatics
要約(日本語): エレキテルは1765年に「紅毛談」によって医療器具として紹介され,平賀源内が1776年に復元に成功し.これが日本初の電気機械となった.その後エレキテルは国内で量産され,庶民はそれを使った見世物を楽しみ,知識人は科学的な装置としてとらえ,これを用いて自然現象を解明しようとした.本稿では江戸時代の文献に基づき,エレキテルの扱われかた,とらえかたについて紹介する.
要約(英語): Erekiteru (friction generator) is the Japan’s first electric machine. In late Edo period, sometimes Erekiteru were used in show business and people at that time enjoyed it. On the other hand, intellects at that time thought that Erekiteru were scientific instruments to simulate natural phenomena.
原稿種別: 日本語
PDFファイルサイズ: 2,308 Kバイト
受取状況を読み込めませんでした